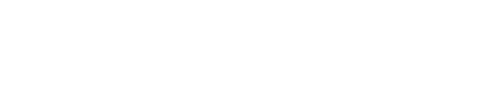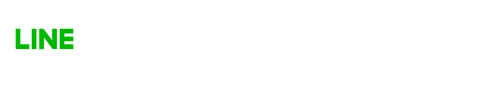-
省エネモードを使う
エコキュートの省エネモードを使いこなせば、必要な量だけ沸かすことができて無駄がありません。
各社のエコキュートで省エネモードが設定されていますが、例として三菱電機の下表をご参照ください。
参考:わき上げ制御-三菱電機
三菱電機の省エネモード「おまかせ」は過去2週間の使用量を学習し、最適な湯量を算出して夜間に自動で沸かします。
必要量以上に沸かし過ぎることがないため、電気代を節約できる機能です。
また、夜間に沸かした湯量が翌日足りなさそうな場合に、お湯が切れそうな見通しがたつと自動で沸き増しをおこなう機能があります。
洗い物やシャワーの途中で湯切れしてしまうことがないので、省エネモードにしていても快適に使用可能です。
ただし、省エネモードだと寒い時にお湯を多く沸かす、暑い夏はシャワーなので湯量を減らすなどの微調整ができません。
夏や冬の季節によって設定を変更し、湯量を調整するのがおすすめの使い方です。
-
電気代が安い時間帯に使う
電気代が安い夜間の時間帯に使うこともエコキュートのコストを抑える方法のひとつです。
例として、東京電力、関西電力、中国電力の料金プランをまとめました。
下表は東京電力の「スマートライフ」の料金プランです。
| 時間帯区分 |
1kWhあたりの料金(税込) |
| 午前6時~午前1時 |
35.76円 |
| 午前1時~午前6時 |
27.86円 |
東京電力の夜間と日中の料金と比較すると、夜間の料金の方が8円ほど安くなっています。
参考:スマートライフ-東京電力エナジーパートナー
下表は関西電力の「はぴeタイムR」の料金プランです。
| 時間帯区分 |
1kWhあたりの料金(税込) |
デイタイム(夏期:7/1~9/30)
平日 午前10時~午後5時 |
28.87円 |
デイタイム(夏期除く期間)
平日 午前10時~午後5時 |
26.24円 |
リビングタイム(生活時間)
平日 午前7時~午前10時
平日 午後5時~午後11時
土日祝日 午前7時~午後11時 |
22.80円 |
ナイトタイム(夜間時間)
毎日 午後11時~午前7時 |
15.37円 |
関西電力のデイタイム(夏期)の料金とナイトタイムの料金を比較すると、ナイトタイムが13円ほど安いです。
参考:はぴeタイムR-関西電力
下表は中国電力の「ぐっとずっと。プラン」の料金プランです。
| 時間帯区分 |
1kWhあたりの料金(税込) |
デイタイム(夏季:7/1~9/30)
平日 午前9時~午後9時 |
46.46円 |
デイタイム(その他季:4/1~6/30・10/1~翌年3/31)
平日 午前9時~午後9時 |
44.40円 |
ナイトタイム
平日 午前0時~午前9時
平日 午後9時~午前0時 |
30.35円 |
ホリデータイム
土曜・日曜・祝日、1/2~1/4、5/1、5/2、12/30、12/31の全日 |
30.35円 |
中国電力のデイタイム(夏期)の料金と比較すると、ナイトタイムとホリデータイムが16円ほど安くなっています。
参考:ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース-中国電力
いずれのプランも、同じ湯量を沸かすのであれば夜間や土日祝日に沸かすほうが圧倒的にお得なため、デイタイム(日中)に追加で沸かさないように使用湯量を調整するのが料金を抑えるコツです。
調整方法としては、洗い物をする際にお湯を流しっぱなしにしない、温度を低めに設定して使用するなどがあります。
貯湯タンク内の残量はタッチパネルで確認できるため、少ない時は洗濯・乾燥を夜間にするなど工夫してください。
-
他の家電を使う時間帯を変える
エコキュートを夜間に使っても電気代が下がらない場合は、その他の家電を日中に使い過ぎている可能性が考えられます。
電子レンジや洗濯機・乾燥機、エアコンなど消費電力の大きい家電を日中に使い過ぎると、エコキュートによる電気代の削減効果はあまり実感できないでしょう。
例えば、洗濯機や乾燥機の使用など、日中でなくてもいいものを夜間にシフトすると電気代を抑えられます。
一方、誰かが在宅していることや日中におこなう家事が多いご家庭であれば、太陽光発電と併用する方法もあります。
近年は各メーカーから太陽光発電と連携できるエコキュートが発売されています。
日中の電力を太陽光発電で補い、余った電力を夜間にエコキュートで使用すれば効率的な電力消費が可能になるでしょう。
太陽光発電と併用する場合は、お湯の沸き上げ時間がデイタイムに重ならないよう調節する必要があります。
-
タンクの設定温度を下げる
季節にあわせて貯湯タンクの設定温度を調節すると、電気代を無駄にせず給湯できます。
エコキュートで沸かしたお湯の各所への給湯は、水を混ぜて調温してから送る仕組みです。
貯湯タンクから蛇口までは配管を通るため、お湯の温度が3℃前後下がります。
ぬるく感じるとお湯を大量に使ってしまうことがあるため、適温に設定することが重要です。
水道水の温度は季節によって変わるため、夏場は「沸き上げ温度を下げる」または「沸かす湯量を少なめに設定する」と電気代も水道代も無駄にせず効率よく給湯できるでしょう。
一般的に、節電を意識しない場合の給湯温度は60度、節電を意識する場合の給湯温度は50度設定くらいが丁度いいといわれています。
沸かす湯量については、多くのメーカーで自動調節機能がついているため、導入予定のメーカーの機能をご確認ください。
-
自動沸き増し機能を停止する
エコキュートに「自動沸き増し機能」がついている場合は、停止しておくと電気代の節約になります。
自動沸き増し機能とは、タンクの湯量が不足しそうな時に自動で日中に沸き増しをする機能です。
デイタイム料金の日中に沸かすと電気代が割高になるため、なるべく日中に湯切れしないよう使用湯量を調節しましょう。
来客やシャワー・お風呂など途中で湯切れすると困る場合は、あらかじめ湯量の確認が必要です。
自動沸き増し機能を停止していても、もしお湯が足りなくなりそうであれば手動で沸かすこともできます。
-
ピークカット設定をする
エコキュートのピークカット設定をしておかないと、電気代が高額になってしまう可能性があります。
夜間の電気料金が安いプランの場合、単価が高い日中の時間帯は「ピーク」と呼ばれます。
契約している電気料金プランの「ピーク」の間は、お湯が少なくなっても自動沸き増しをしない設定が「ピークカット設定」です。
ご自宅のエコキュートにピークカット設定がある場合は活用し、ピークカット設定がない場合はピーク時間帯を外して沸き増ししましょう。
-
追い焚きではなく高温足し湯をする
お風呂のお湯を温める際は、追い焚きや自動保温ではなく「高温足し湯」がおすすめです。
追い焚きや自動保温は、タンク内の熱を使ってぬるくなったお湯を循環させて温め直す仕組みのため、その分タンク内の熱がなくなってしまいます。
高温足し湯はタンク内の熱いお湯をそのまま足すのでタンク内の熱は下がりません。
ぬるいお湯を循環させて温める追い焚きや自動保温より、高温足し湯のほうが省エネで経済的です。
自動保温をして浴槽の温度を保つご家庭も多いですが、エコキュートを導入しているのであれば、ぬるくなったと感じた時点で高温足し湯をしましょう。
-
お風呂は間隔を空けずに入る
ぬるくなったお風呂の温度調整には、いずれの方法でも多少はタンク内の熱を使うため、ぬるくなる前にお風呂に入ってしまうのが一番節約になります。
そのため、なるべく間隔を空けず、家族みんなで同じ時間帯にお風呂に入ることをおすすめします。
エコキュートのメーカーにもよりますが、保温は自動の場合が多いため、自動保温機能はオフにしましょう。
自動保温をオフにしても、湯船にふたをしておけば一定時間は温かさをキープできます。
ただし、自動保温をオフにして長時間経過するとお湯が完全に冷め、高温足し湯では十分に温まらない場合があります。
その場合は追い焚きか再度湯張りをしてください。
メーカーによって、入浴しながらゆっくり追い焚きするモードや、急速で追い焚きするモードがあります。
急速の追い焚きは消費電力が増えるため、水温が低い場合は再度湯はりをしたほうが省エネです。
-
毎日新たに湯はりする
前日の残り湯を追い焚きして再利用しているご家庭もありますが、エコキュートの場合は毎日新たに湯はりするほうが経済的です。
完全に冷めきったお湯をエコキュートの追い焚きで温め直すと、貯湯タンク内のお湯が不足したりお昼に追加で沸かす必要があったりします。
前日の残り湯がもったいないと感じる方は、洗濯など他の用途に活用するのがおすすめです。
-
不在設定を使う
旅行などで長期間お湯を使わないときは、沸き上げ運転を止める「不在設定」「休止設定」などがおすすめです。
設定期間は運転が⽌まり無駄な沸き上げをしなくなるため、電気代を節約できます。
帰宅前夜に運転を開始する設定にしておけば、帰宅日の日中からお湯を使えます。
-
エコキュートのタンクを大きめにする
エコキュートで最も避けたいのは、日中にタンク内のお湯がなくなり電気代が割高な日中にお湯を沸かすことです。
容量が大きい機種を選ぶと本体価格が10万円程度高くなりますが、より多く貯湯できるため、電気代のランニングコストを抑えられます。
4人家族の場合、タンク容量は370L・460Lが選択肢となります。
余裕をもって460Lにしておくと、湯切れを起こす可能性が低いでしょう。
また、世帯人数ぎりぎりのタンク容量にすると、こまめにお湯の残量を確認したり使用量を調整したりと手間がかかります。
使い始めてから不足することが分かったり、災害など不測の事態に湯切れを起こしたりする可能性も高いです。
湯切れを防ぐために、世帯人数にあわせて想定使用量よりも少し大きめのタンクを選びましょう。